分子栄養学と腸内環境「短鎖脂肪酸は免疫のカギ!腸内環境改善で健康な身体づくり」


皆さんは「短鎖脂肪酸」が、免疫のカギとなることをご存じですか?
短鎖脂肪酸は、腸内細菌が食物繊維などを発酵して作る代謝産物(酪酸、プロビオン酸、酢酸など)のことです。食物繊維は少なくとも1日25g以上の摂取が厚生労働省より推奨されています。
今回は、
・短鎖脂肪酸とインフルエンザ感染の際の免疫の関係
について一緒に見ていきましょう。
腸内細菌がうみ出す「短鎖脂肪酸」

私たちの腸には、約100兆個の腸内細菌がすんでいるといわれます※1。
そして腸内細菌の中には
・ビタミン
・短鎖脂肪酸
をつくり出すものが存在します。今回は、このうちの短鎖脂肪酸のお話です。
腸内環境を整えてインフルエンザ対策!? 食物繊維と免疫の意外な関係
豊富な水溶性食物繊維の摂取が、短鎖脂肪酸を増やして免疫のバランスを整え、インフルエンザによる感染を抑制するという研究が発表されています※2。
この研究では、マウスの実験において、
・水溶性食物繊維の摂取
↓
・ビフィズス菌など有用菌の勢力が刺激され、腸内細菌叢のバランスが大きく変化
↓
・腸内の短鎖脂肪酸(酪酸、プロピオン酸、酢酸)が増加(特に酪酸が増加)
↓
・短鎖脂肪酸が宿主※3の免疫システムを強化し、インフルエンザ感染に対して抵抗性を獲得
ということが報告されています。この研究では、食物繊維と短鎖脂肪酸が免疫システムの以下2点に貢献することが明らかになりました※2。
①自然免疫の過剰な反応を抑制し、組織の過剰な損傷を防ぐ
②インフルエンザに特異的な獲得免疫(CD8+T細胞)を強化
以下に、主に①について一緒に見ていきましょう。
自然免疫マクロファージと好中球の反応は、過剰にならないことが大切
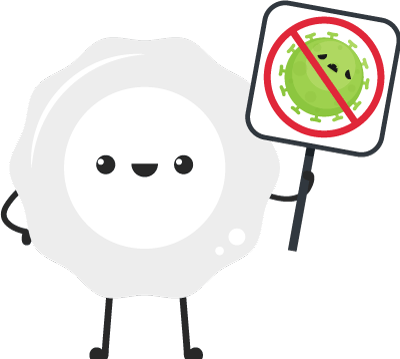
免疫の第2のバリア自然免疫。自然免疫の白血球の中には、マクロファージと好中球が存在します。
(※ビタミンCと免疫)
マクロファージと好中球は、病原体などの侵入者を無差別に攻撃して宿主を守る自然免疫の立役者です。
ただし、マクロファージと好中球の反応は、どちらも過剰にならないことが健康維持にとって大切です。
好中球は、マウスの研究にて
●症状の軽いRSウイルス感染の場合
・感染後 18 時間でピークに達し、感染後 36 時間までにほとんど消失
するのに対し、
●病原性の高いA型インフルエンザウイルス感染の場合
・重症のマウスの肺から、感染後 12 日目でも検出可能
であることが報告されています※4。
好中球の攻撃は非常に攻撃的であるため※4、より多くの好中球がより長い時間肺に存在することが症状の重症化に関与すると考えられています※4。
短鎖脂肪酸が、自然免疫の過剰な反応を抑制+獲得免疫を強化
今回の研究では、水溶性食物繊維の摂取によって増えた短鎖脂肪酸が、インフルエンザ感染時の自然免疫において
・マクロファージの数を増やす
・マクロファージの働きを適正化する
・好中球の過剰な反応を抑える
ことで、組織の損傷を抑えることが示されています※2。
また、第3のバリア獲得免疫においても
・「CD8+T細胞」という、ウイルスと戦う重要な免疫細胞の働きを強化
することが示されています※2。
以上よりこの研究が示唆することは、短鎖脂肪酸はインフルエンザに対する適度の抵抗性を保ちつつ宿主にとって不利な反応を抑制してくれているということです。
短鎖脂肪酸は、インフルエンザ感染の自然免疫と獲得免疫両方において、免疫を適切に調整することが示されています※2。
どのくらいの量の食物繊維を食べればいい? 1日25g以上がお勧め!
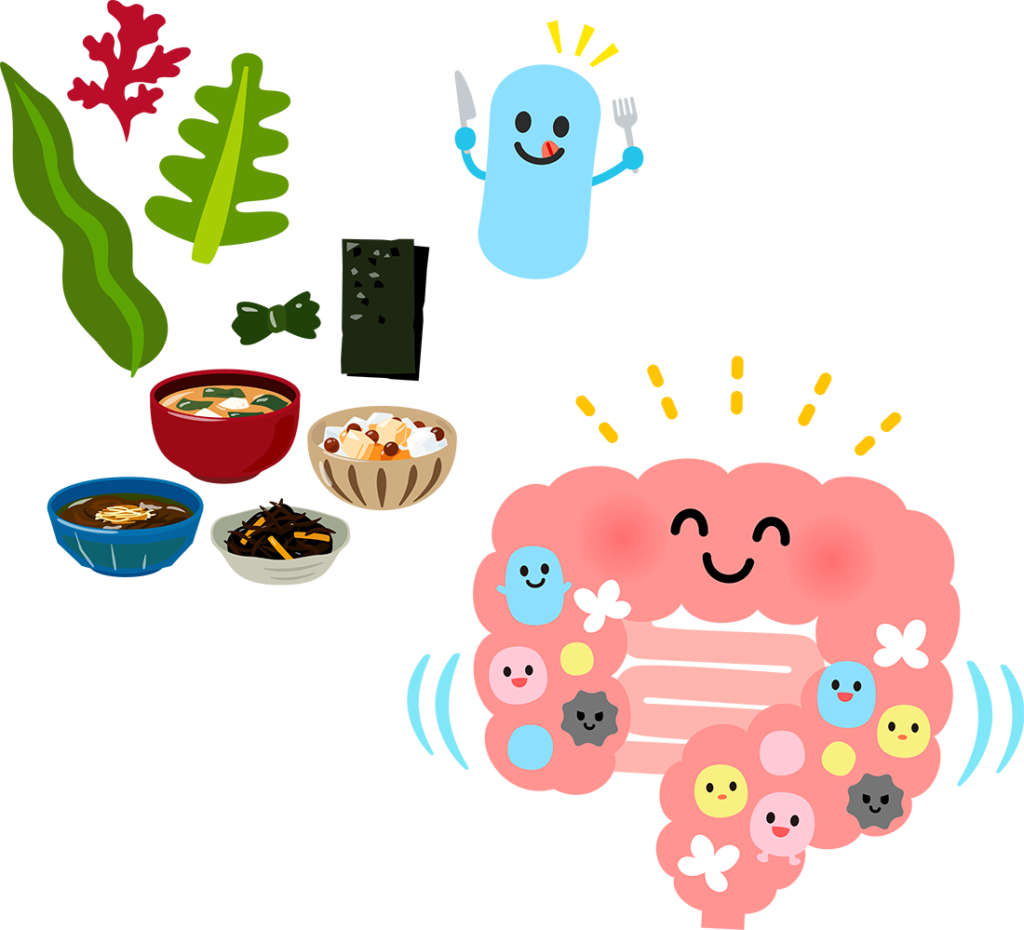
短鎖脂肪酸は、特定の腸内細菌が食物繊維などを発酵することで作り出す代謝産物です。
食物繊維摂取によって短鎖脂肪酸の産生量を変化させることで、さまざまな生活習慣病などの病気を予防する可能性も考えられています※1、※5。
短鎖脂肪酸による恩恵を享受するためにも、多様な種類の食物繊維を食べ、腸内細菌にエサをあげましょう※1。
食物繊維はさまざまな生活習慣病のリスクを下げる可能性が検討されているため、厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では、「健康への利益を考えた場合、「少なくとも1日当たり25g」は食物繊維を摂取した方が良いと考えられる」※6としています。
「日本人の食事摂取基準(2020年版)」の推奨量は1日あたり24g以上でした。その当時よりさらに1g増えていることから、健康にとっての食物繊維の重要性がより一層認識されてきていることが伺えます。
(※食物繊維はどのくらい摂ればいい?)
食物繊維はいろんな食材から摂りましょう

食物繊維は大きく「水溶性食物繊維」「不溶性食物繊維」の2つに分けて考えられています。
水溶性食物繊維は不溶性食物繊維に比べて食品に含まれる量が少ないため、十分に意識して摂る必要があります。
それぞれの食物繊維には別の役割があるため、特定の水溶性食物繊維ばかりを摂らず、自分に合った食物繊維、いろいろな食材を食べましょう※7。
※食物繊維が多いのはどんな食品?では、野菜、海藻、きのこ、穀類・いも類、果物などの食品に、どのくらいの水溶性食物繊維と不溶性食物繊維が入っているか、具体的なグラムがわかります。自分の食事の見直しに、ぜひご活用ください。
分子栄養学における総合的な栄養素による免疫対策
分子栄養学では、感染症に対する免疫対策として、腸内環境を含めた総合的な栄養素によるアプローチを提唱しています。その栄養素とは、
・タンパク質
・グルタミン
・脂質(適切なオメガ3:オメガ6脂肪酸比)
・ビタミン(A、B群、C、D、E)
・ミネラル(鉄、亜鉛、セレン、マンガン、銅)
・プロバイオティクス
・プレバイオティクス(食物繊維など)
などです。これらの栄養素の個体差に沿った至適量によって、免疫の第1・第2・第3バリアに対して総合的にアプローチすることを提唱しています。
(※分子栄養学における免疫と栄養素の基本対策①)
短鎖脂肪酸の力を借りることで免疫のバランスを適切に調整し、タンパク質をはじめとしたビタミン・ミネラルの分子栄養学的至適量摂取により、効率的な感染症対策を行いましょう。
今回のまとめ
短鎖脂肪酸は、インフルエンザ感染の自然免疫と獲得免疫両方において、免疫を適切に調整することが示されています。
短鎖脂肪酸は、腸内細菌が食物繊維などを発酵して作る代謝産物(酪酸、プロビオン酸、酢酸など)のことです。
食物繊維は、少なくとも1日25g以上の摂取が厚生労働省より推奨されています。
短鎖脂肪酸の力を借りることで免疫のバランスを適切に調整し、タンパク質をはじめとしたビタミン・ミネラルの分子栄養学的至適量摂取により、効率的な感染症対策を行いましょう。
※1 Fusco, W.,et al. (2023). Short-Chain Fatty-Acid-Producing Bacteria: Key Components of the Human Gut Microbiota. Nutrients, 15(9), 2211.
※2 Trompette, A.,et al. (2018). Dietary Fiber Confers Protection against Flu by Shaping Ly6c- Patrolling Monocyte Hematopoiesis and CD8+ T Cell Metabolism. Immunity, 48(5),992–1005.e8.
※3 感染を受ける側の動物や植物を宿主(しゅくしゅ)といいます。
※4 Johansson, C.,et al. (2021). Neutrophils in respiratory viral infections. Mucosal Immunology, 14, 815–827.
※5 Tan, JK.,et al. (2023). Dietary fiber and SCFAs in the regulation of mucosal immunity. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 151(2), 361–370.
※6 出典:「日本人の食事摂取基準(2025年版)」策定検討会報告書」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001316464.pdf)(2025年2月4日に利用)
※7 食物繊維は、過敏性腸症候群、SIBOなど病態によって摂り方が変わる場合があります。