分子栄養学の栄養素:ビタミンB群を知る③「ビタミンB群の最適なレベル」はどこに?
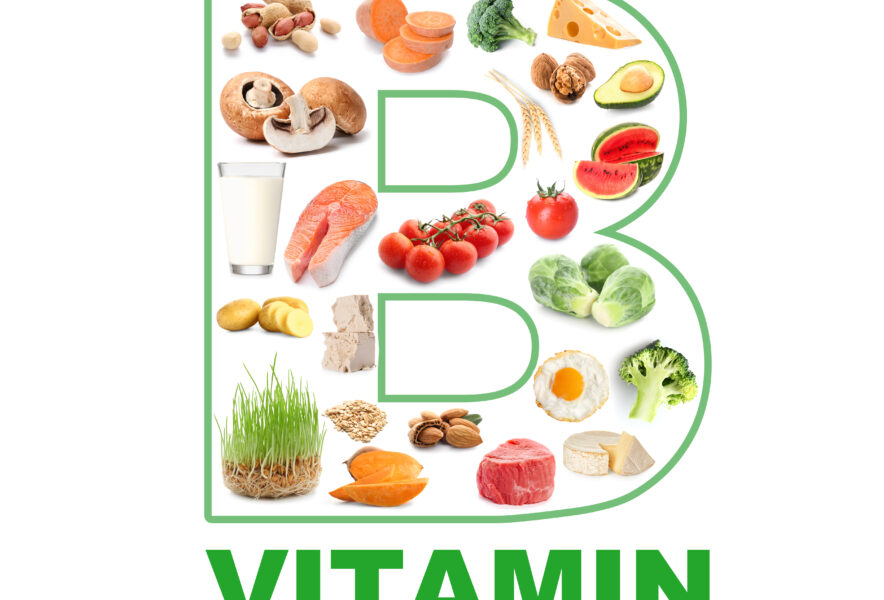

分子栄養学では、体調や健康維持をサポートするための「至適量のビタミンB群摂取」を重要視
分子栄養学では、体調や健康維持をサポートするための適切なキー栄養素として、至適量のビタミンB群摂取を重要視しています。
ビタミンB群は、脳や身体全体にとっての代謝を進める基礎をつくる栄養素です。
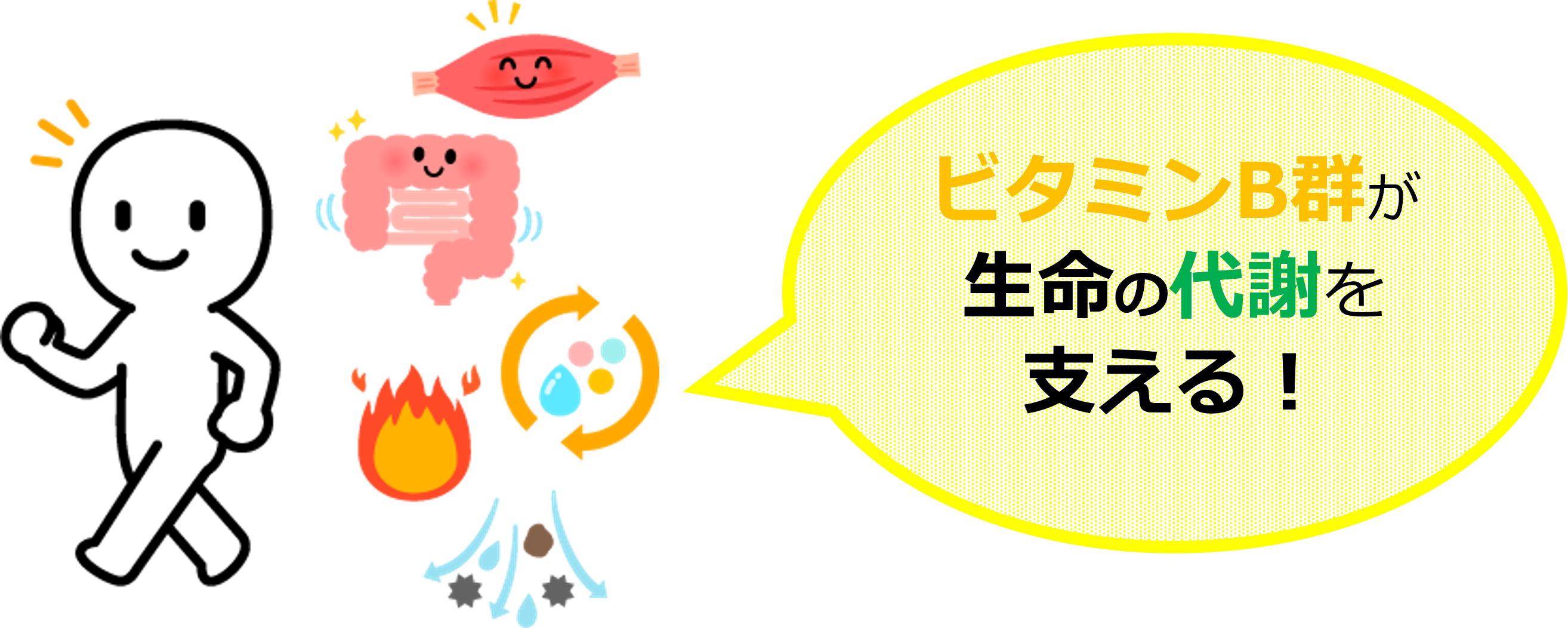
分子栄養学の考えるビタミンB群の至適量とは?
分子栄養学が重要視する至適量のビタミンB群。至適量とは、どんな量を指すでしょう。
「至適(optimum)」というのは、最適条件というような意味です。“個々人に最もふさわしいレベル”と考えていただければわかりやすいでしょう。
一人ひとり、栄養摂取の至適量は異なります。また、一生不変のものではなく、年齢、環境、ストレス状況などに応じて至適量はどんどん変わります(※分子栄養学とは⑥)。
そこで、「そのとき、その人に最適と言える個々の栄養バランスを整えることが、健康維持につながるのではないか」というのが分子栄養学の考えです。分子栄養学では、個体差に沿った栄養素の至適量というものをとても大切にしています。
また、ただ単に栄養素を摂取する量だけではなく消化・吸収できた量によって至適量が維持されると考えられることから、栄養素の消化・吸収をつかさどる胃腸の状態を最も重要視しています。腸内細菌の中のある種の有用菌はビタミンB群を合成し、ヒトに供給してくれる存在です(※ビタミンB群を知る①)。
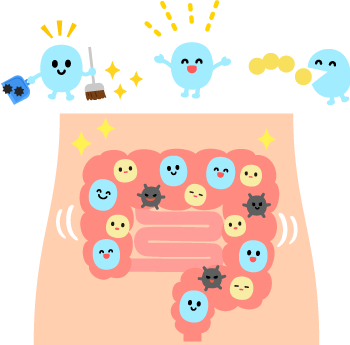
ビタミンB群の「最適なレベル(the optimal level)」はどこに?
「ビタミンB群をどのくらい摂ったらよいのか?」
これまでの歴史において、その量については、今現在 通常の栄養学で言われるそれぞれの欠乏症を予防するための摂取量について明らかにされてきました(※ビタミンB群を知る①「ビタミンB群は8種類ある!」)。
しかし欠乏症を予防できる量を摂ったとしても、ビタミンB群「最適なレベル(the optimal level)がどこにあるのか」については、全く明らかにされていないことが指摘されています※1。
そんな中、「欠乏症まではいかないが、最適なレベルではない潜在性欠乏症(marginal deficiency)の栄養状態のリスクについて、アメリカ政府が公的に認めている」※1ことが報告されています。
そこで言われる「最適ではない摂取量のレベル」とは、各ビタミンの欠乏症を予防する量以上の摂取量を指しています※1。
ビタミンの欠乏は、農耕が始まる以前の食事と現代の食事の差によるもの?
農耕が始まる以前の人の食事は、野菜、果物、ナッツ類、魚、肉などが中心でした。
しかし現代では、大量の砂糖や精製穀物、加工肉などをはじめとするビタミンやミネラルといった微量栄養素の含有量の少ない いわゆる「西洋の食事パターン」を食べていることの違いが、ビタミンの欠乏症、肥満、心血管疾患などの病気の基礎となっているのではないかと数々の論文で指摘されています※1、※2、※3、※4。
ある論文では、「先進国では、かなりの割合の人々がビタミンB群の欠乏・不足に悩んでいる」ことが報告されています※1。
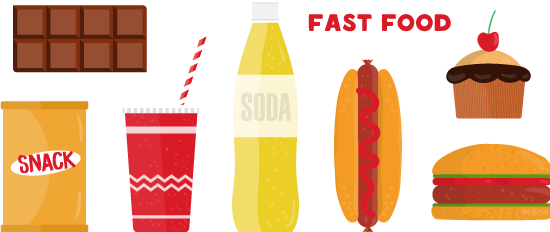
脳の健康を維持するビタミンB群の摂取量はどのくらい?
ビタミンB群の摂取量について、「国が勧める量を大幅に超える量で摂取することが、脳の健康を維持するための合理的なアプローチとなる可能性」が指摘されています※1。
その中ではこうも述べられています。「一般的に、先進国に住む人々は日々適切な栄養を摂取しており、栄養素の欠乏はないと考えられがちです。しかし国の定める「食事摂取基準」による「推奨量(ほとんどの者が充足している量)」は、欠乏症を予防することだけを指しています。そして先進国に住む人々の中には、その推奨量の量でさえ摂っていないことがある」※1との指摘です。
「医薬品の摂取・肥満・激しい運動・年齢、遺伝子多型・民族性・甲状腺機能の不全・代謝経路の不全などが関係し、ビタミンの消化・吸収・排泄には個体差が認められることが明らかになっている。それらに応じて栄養素の必要量は変化するはずであるにも関わらず、過去40年に渡って、国によって定められている必要量が変化していない」※1ことが問題として指摘されています。
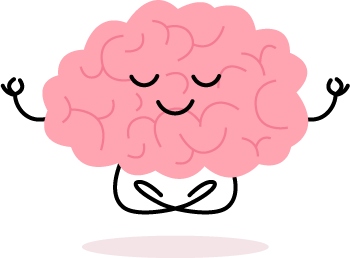
分子栄養学は医師が行う血液検査モニタリングなどで、至適量のビタミンB群摂取を目指す
分子栄養学では、健康維持増進の基本として
・エネルギー産生(ミトコンドリア機能)を効率的に進めるためのビタミンB群
を栄養素アプローチの基本として重要視しています。私たちが生きる上で、エネルギー(ATP)は最も基礎となる重要項目だからです。
私たちは食事をしたり、考えたりといった活動をするためにATPを常に消費するため、常にATPを産生し続ける必要があります。
健やかな身体、健やかなココロ。これらはすべてエネルギーがあってこその健康です。
医師による詳細な問診や血液検査などにより、個体差に沿ったビタミンB群をはじめとした栄養素の至適量補給で、効率的な自分自身の健康管理を目指します。
(※「ビタミンB群は8種類ある!」)(※「ビタミンB群は8種類一緒に摂ることが合理的!」)
※1 Kennedy, DO. B Vitamins and the Brain: Mechanisms, Dose and Efficacy—A Review. Nutrients, 8(2): 68. (2016)
※2 Cordain, L.,et al. Origins and evolution of the western diet: Health implications for the 21st century. American Journal of Clinical Nutrition, 81(2):341-354. (2005)
※3 Benzie, IFF. Evolution of dietary antioxidants. Comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular & Integrative Physiology, 136(1):113-126. (2003)
※4 Milton, K. Back to basics: why foods of wild primates have relevance for modern human health. Nutrition, 16(7-8):480-483. (2000)