年末年始に向けた正しい身体づくり「脂肪肝対策②」

美味しいものを食べる機会の多い年末年始。
今回は、内臓脂肪・脂肪肝を予防する身体づくりについて、分子栄養学で考えられる対策を一緒に見ていきましょう。
運動不足や糖質・脂質過剰で起こり得る内臓脂肪・脂肪肝。※年末年始に向けた正しい身体づくり「脂肪肝対策①」では、脂肪の役割や種類、脂肪肝になる仕組みなどをお伝えしています。
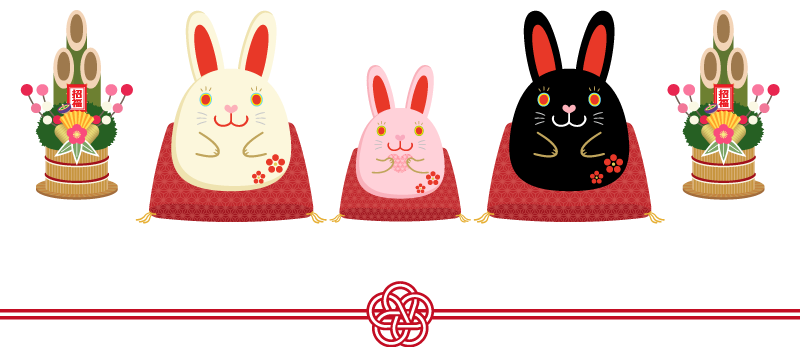
分子栄養学的対策①:まずは自分の今の状態を知る
自分で太ったな、と思っても、実はタンパク質不足でむくみが起こっている可能性もあるかもしれません。
そこで、適切な栄養状態による最適な健康状態を保つために、まず自分の今の状態を詳細な血液・尿検査で知ることをご提案します。(※血液検査の意義①)。
詳細な血液検査などの結果は、如実に「今」の自分を表します。分子栄養学実践医師によるモニタリングのもと、自分に必要な対策「筋肉を増やす」「脂肪を燃やす」といった具体的な作戦を立てましょう。
筋肉はいちばんのエネルギー消費器官
いかに楽して食べた分を消費するかを考える場合、活躍してくれるのが筋肉です。なぜかというと、1日の消費エネルギー量のうち、筋肉が最もエネルギーを消費してくれる器官だからです。 1日の消費エネルギー量は、基礎代謝という部分が約60%を占め、その中で筋肉によるエネルギーの消費がいちばん多くなっています※6。総エネルギー消費量(24時間相当)は、大きく基礎代謝量(約60%)・食事誘発性熱産生(約10%)・身体活動量(約30%)の3つで構成されています※7。基礎代謝とは、生命活動を維持するために最低限必要となるエネルギーのことです。
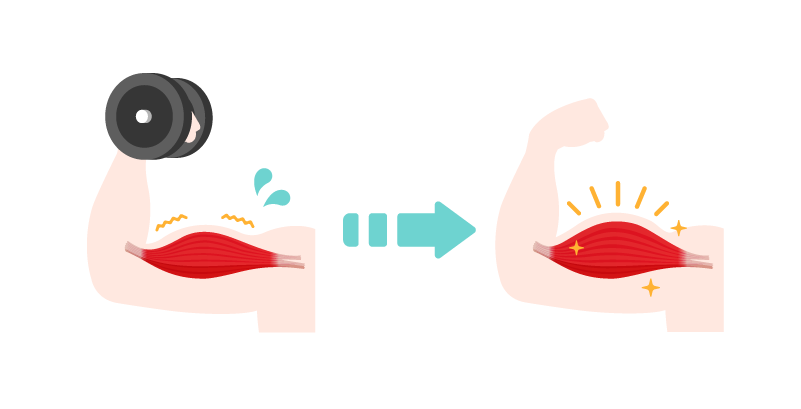
分子栄養学的アプローチ②:バランスの良い食事をよく噛んで食べましょう
分子栄養学的な脂肪肝対策の2番目として考えられるのが、バランスの良い食事です。
エネルギーを消費してくれる筋肉量の維持には、適切なエネルギー量とタンパク質の補給が大事です。自分の活動量に合った食事の量を食べましょう。
それではどのくらいのタンパク質を食べたらよいでしょう。分子栄養学でお勧めしているタンパク質の量は、1回の食事で手のひらにのるくらいが目安です。
また、よく噛むこともお勧めです。よく噛むことでタンパク質が物理的に小さく細かくされてから胃に行くため、胃の中でタンパク質が消化されやすくなり、それが下流にある腸内環境を整えることにもつながるからです。
このほか、適正な糖質量、青魚やアマニ油などのオメガ3系の脂質を積極的に摂り、食前に野菜、海藻、きのこなどの食物繊維をたっぷり食べましょう。おかずを先に食べて血糖値の急な上昇を防ぐことで中性脂肪を下げることにつながる可能性があります。
分子栄養学的アプローチ③:効率の良い代謝のためのビタミン・ミネラルを一緒に
分子栄養学的な脂肪肝対策として考えられるのが、ビタミン・ミネラルの補給です。
エネルギー産生栄養素(3大栄養素)からエネルギーや新しい細胞をつくったり、全身で行われる代謝には酵素が必要です。そしてそのほとんどの酵素が働くために、ビタミン・ミネラルが補因子として活躍します。
分子栄養学では、ビタミン・ミネラルが足りないことで糖質や脂質の代謝が円滑に行えず、せっかく摂った3大栄養素をエネルギーに換えられずに脂肪として蓄積しやすくなる可能性を考えています。
効率の良い代謝のため、至適量のビタミン・ミネラルを一緒に摂りましょう。

分子栄養学的アプローチ④:腸内環境を整える短鎖脂肪酸
分子栄養学的な脂肪肝対策の4番目として考えられるのが、腸内環境を整えることです。
脂肪肝の原因のひとつとして、腸内環境の悪化、リーキーガット症候群などが注目されています。
リーキーガット症候群とは腸の細胞と細胞の間にすきまができることで腸管バリア機能が落ち、本来なら通らないものまで通ってしまった結果、腸や全身で炎症を起こしたりしてしまう状態のことを指しています。
腸内環境の整備は、腸の中にすんでいる腸内細菌のバランスや多様性を整えることがひとつのポイントです。
身体に良い影響を与える生菌として、乳酸菌、酪酸菌、ビフィズス菌などが有名です。(※子供の栄養「腸は全身をコントロールする第2の脳」)これらの菌が水溶性食物繊維やオリゴ糖などを発酵して短鎖脂肪酸を作ります。
短鎖脂肪酸は、腸粘膜を整え※8、脂肪酸合成を抑制し※9、食欲を調節してくれることで※10肥満を予防する役割が期待されています。また、炎症を抑制し※11、免疫機能の調整をしたり※12、全身の健康状態に関わっているといわれます。
腸内細菌のエサとなるさまざまな食物繊維をよく噛んでたっぷり食べ、自分のおなかの中に合った良い菌のお花畑を咲かせましょう。SIBO(小腸内細菌異常増殖症)の方は食べられる食品が変わる場合がありますので、医師の助言を得ながら自分に合ったものを選択してください。
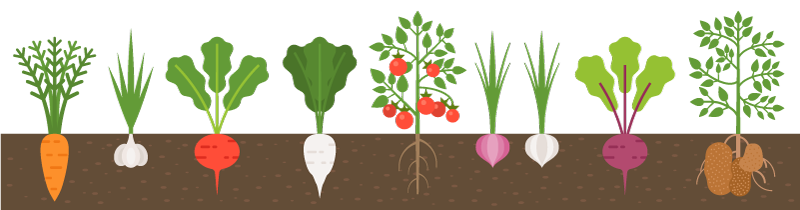
分子栄養学的アプローチ⑤:良い睡眠と適度な運動
分子栄養学的な脂肪肝対策の5番目として考えられるのが、良い睡眠と適度な運動です。
悪い睡眠と非アルコール性脂肪肝疾患の関係が指摘されています※13。
健康な成人男性を対象とした研究では、睡眠時間を4時間に制限すると食欲抑制ホルモン(レプチン)が減少し、食欲を促進するホルモン( グレリン)の上昇がみられるため、食欲が増えることがわかっています※14。また良い睡眠をとることで体調も整います。
運動面では、内臓脂肪や脂肪肝改善に適度な運動が勧められています。軽い筋トレで筋肉量を維持し、ウオーキングで脂肪を燃やしましょう。
ただし体調や抱える病気の状態によって、「適度な運動」の内容は変わります。ぜひ1年に1回、医療機関で自分に起こる変化や体調を把握しながら、自分にとっての適切な運動を続けましょう。
忘年会、クリスマスが終わったと思ったら、お正月、新年会とアルコール、ご馳走、スイーツなど、ついつい食べ過ぎの機会が増えるこの季節。
そんな中でも適切な量のタンパク質、ビタミン・ミネラルと適度な運動で脂肪を燃やし、筋肉を維持し、食物繊維をよく噛んで食べることで腸内環境を整えて、素敵な新年を迎えましょう。
※6 厚生労働省eヘルスネット https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise/s-02-004.html 「表2: ヒトの臓器・組織における安静時代謝量」参照 大河原 一憲 ※7 厚生労働省eヘルスネットより引用 https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise/s-02-003.html 大河原 一憲 ※8 Kelly C. J.,et al. Crosstalk between Microbiota-Derived Short-Chain Fatty Acids and Intestinal Epithelial HIF Augments Tissue Barrier Function. Cell Host Microbe. 17(5) :662-71.(2015) ※9 Shimizu H.,et al. Dietary short-chain fatty acid intake improves the hepatic metabolic condition via FFAR3. Scientific Reports, 9: 16574. (2019) ※10 Chambers E.S. , et al. Effects of targeted delivery of propionate to the human colon on appetite regulation, body weight maintenance and adiposity in overweight adults. Gut,64(11):1744-1754. (2015) ※11 Nastasi C., et al. The effect of short-chain fatty acids on human monocyte-derived dendritic cells. Scientific Reports,5: 16148. (2015) ※12 Kim M., et al. Gut Microbial Metabolites Fuel Host Antibody Responses. Cell Host Microbe, 20(2):202-214.(2016) ※13 Marjot T., et al. Sleep and liver disease: a bidirectional relationship. Lancet Gastroenterol Hepatol, 6(10):850-863. (2021) ※14 Spiegel K.,et al. Brief communication: Sleep curtailment in healthy young men is associated with decreased leptin levels, elevated ghrelin levels, and increased hunger and appetite. Annals of Internal Medicine,141(11):846-850. (2004)