分子栄養学とは⑧「分子栄養学に基づく栄養療法の得意分野」

分子栄養学に基づく栄養療法の得意分野
分子栄養学に基づく栄養療法(以下、栄養療法と略します)と、健康保険で認められる一般的な薬を用いた治療。今回は、この2つの役割分担について考えます。
栄養療法の得意なところと、健康保険で認められる治療法の得意なところ、それぞれ得意分野が存在します。
栄養療法が得意なのは、「栄養素の不足」や「栄養素の活躍の場」が関わる場合
栄養療法において、健康維持に役立つ栄養素によるアプローチは、その原因となるところに「栄養素の不足」や「栄養素の活躍の場」が関わると考えられる場合です。
分子栄養学は、1つひとつの細胞機能が最高の状態で行われるような栄養素の量とバランスを考慮し、それらの栄養素をしっかり補給することで細胞が正常に機能できることを目指す学問です。そしてその栄養素の力を超えたところで起こるものは、薬の力を借りることも考えます。
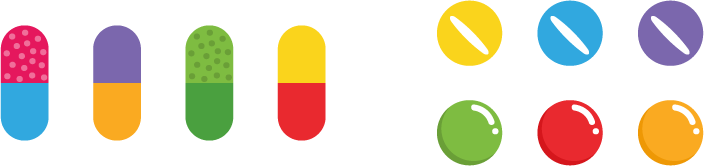
例)風邪を引いたときの対処法
例として、風邪を引いた時の対処法について考えてみましょう。
風邪とは、正しくはかぜ(風邪)症候群のことです。急性上気道炎とも呼ばれます。ウイルスや細菌が上気道(鼻やのど)に感染して起こる急性炎症をまとめてそう呼びます。症状としては、咳、くしゃみ、鼻水、のどの痛み、発熱、全身倦怠感などがあります。
風邪を引いた、風邪っぽい、というとき。みなさんはどのように対処しますか?
温かな食事と水分を摂り、暖かくして眠る。
お医者さんに行き、薬局で薬をもらって家に帰る。
栄養素のバランスの整ったごはんを食べて十分な水分を摂り、暖かくして眠るだけで症状が和らぐ場合もあります。また薬を飲むことでくしゃみや鼻水がおさまったり、熱が下がったりすることもあります。
人のもつ能力、自然治癒力
この風邪のときのくしゃみ、鼻水、熱などの症状は、ウイルスなどの病原体から自分を守るために免疫が働いてくれている証拠です。この時 身体の中ではウイルスを追い出そうとしたり、白血球が侵入してきた病原体をぱくぱく食べて処理してくれたり、抗体というタンパク質を作って病原体を攻撃してくれたりしています。
このように、身体にはもともと自然に治ろうとする力(自然治癒力)が備わっており、このことは、人のもつ能力のひとつと考えられています。栄養素のバランスの整ったごはんを食べて十分な水分を摂り、暖かくして眠るだけで症状が和らぐ場合には、その力が存分に発揮され、身体が病原体に打ち克った賜物といえるでしょう。
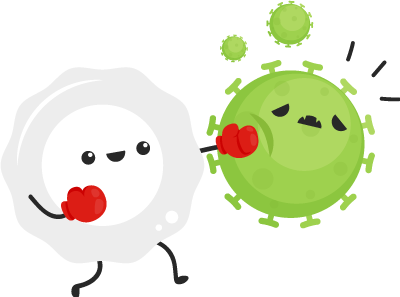
薬の得意分野
一方、暖かくして眠っても治らずに、薬に頼ると症状が収まることがあります。
そんな時、薬は自然治癒力を超えたところで起こる症状を抑えて身体を助けてくれる役割をします。ただしほとんどの風邪薬は症状を抑えますが、風邪そのものを治すわけではありません。あくまで治してくれるのは、白血球などが活躍するもともと身体に備わったしくみ、免疫です。
薬は強く出る症状を強い力で抑え、自然治癒力を回復するための余白を作る手伝いをしてくれます。薬はほとんどの場合安いですし即効性があり、すぐに効くのでとても助かります。
ウイルスや細菌から自分を守るために起こる炎症を身体の中で起こる「火事」と例えると、その火事をホースで大量の水をかけ、一気に鎮圧してくれるのが薬の役割です。

分子栄養学の得意分野
一方、栄養療法では、その燃えた土台をもう一度基礎から建て直す、というのが得意です。また、燃えないように身体を常時メンテナンスしたり、出た火が燃え広がりすぎないような身体の組成を目指すことも考えます。
そしてその際には個体差に沿った、その方にとっての最適な量(至適量)の栄養素が必要です。そしてその個体差を見極めるため、適切かつ詳細な血液検査などによる医師のモニタリングが必要です。
その考え方を応用した、こんな症状は栄養療法の得意分野です。
・まわりの人は大丈夫なのに私だけ風邪を引きやすい
・1年に何回も風邪を引いてしまう
・風邪を引くと長引いてしまう。
こういったときこそ、栄養療法の出番です。
栄養療法では、薬とは別の角度からの健康維持のためのアプローチを試みます。もともと身体に備わる風邪の原因となるウイルスや細菌などから身体を守ってくれる「免疫」という素晴らしい仕組み。その免疫が細胞レベルで十二分に活躍するに足る栄養素の至適量に達しているか、そんなところからアプローチを考えます。
栄養療法のアプローチ
それでは以下に、風邪に負けない身体づくりのための栄養素として、分子栄養学で何が考えられるかを一緒に見ていきましょう。
例えば、免疫の最前線で働いてくれる白血球の仲間、好中球。
好中球は、免疫の最前線で素早く感染部位に移動して無差別に病原体と戦います。そして、好中球は戦い終わると速やかに自死するようにプログラムされています。
その好中球の消費を補うために、骨髄は好中球の産生を増やします。役目を終えた好中球に代わり、常に新しい好中球を作り続けなければ、全体としての免疫能が落ちてしまいます。
そこで分子栄養学では、骨髄が好中球などの白血球をつくり続けるために、新しい細胞の材料となるタンパク質がまず足りているかを考えます。タンパク質の指標ともなるアルブミンは、薬を運ぶ役割も担います。
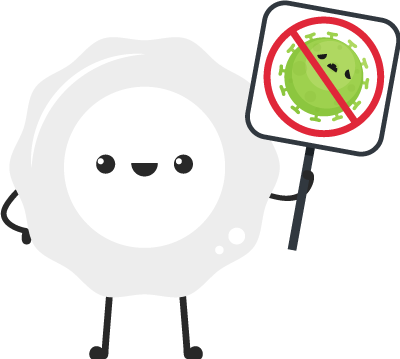
また「白血球が闘う」「新しい細胞が生まれる」ということは、闘い続け、新しい細胞を産生し続けていくためのエネルギーが必要です。
そのエネルギーを得るためには、エネルギー代謝経路をどんどん動かしていかなければなりません。白血球の種類によって使うエネルギー代謝経路が異なるという報告もありますが、細胞が使うための基本的なエネルギー代謝経路にはタンパク質である酵素が関わり、さらにマグネシウム、ビタミンB群、CoQ10、鉄などが関与します。
また電子伝達系というエネルギー代謝経路には酸素が必須となるため、酸素を運搬する赤血球が必要です。いつも適正な大きさ、かつしっかりとした量のヘモグロビンを含んだ赤血球が、十分量の酸素を運んでくれている必要があります。そのため、風邪に負けない体調維持のためには、健全な赤血球産生のための栄養素も重要です。
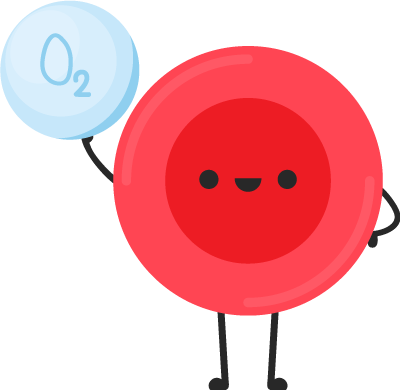
また他の例として、体調維持のためには健康な「粘膜」について見てみましょう。
粘膜とは、私たちの身体の目や鼻、喉、胃や腸などの表面を覆う薄い膜のことです。粘膜は常に「外」と接し、いつでも入ってくる可能性のある外敵から守ってくれる免疫の第一のバリアです。
その粘膜においても、粘膜免疫として最前線で分子レベルの研究が進んでいます。粘膜免疫との関わりのある栄養素として、ビタミン(A、C、D、E)、ミネラル(亜鉛、セレン)、グルタミン、脂肪酸などが注目されています※1。
さらに、免疫細胞の働きを良くしておくために腸内環境を常に整えておくことも重要視します。腸を整えておくことで栄養素の吸収も良くなりますし、善玉菌がビタミンB群などの栄養素も作ってくれます。腸を整えておくことは、体調維持にとって一石二鳥以上の価値があります。
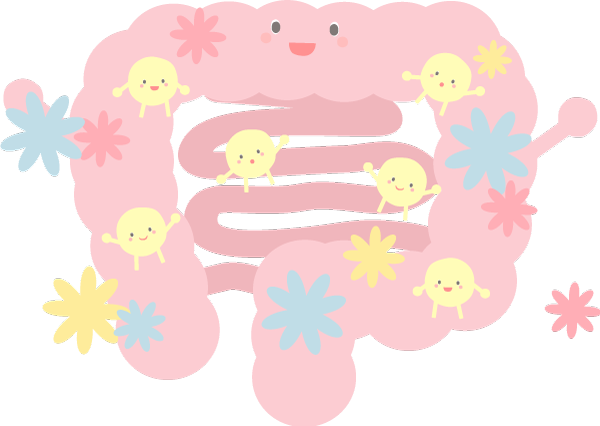
分子栄養学では、分子(栄養素)のバランスと最適な量が健康維持へのツール
分子栄養学では私たちの健康維持増進のためのツールとして、薬ではなく、すでに私たちの身体の中にある分子(栄養素)を用います。
そしてその分子の濃度を各細胞が必要とするバランスと最適な量(至適量)まで高めることによって、身体全体の細胞単位の機能を正常化させ、各細胞が最大限に機能を発揮できることを目指します。
分子栄養学の目指す “オプティマムヘルス(最適な健康)レベル” とは、激しいストレスやどのような環境の変化においても、常に健康を維持できるということです。
遺伝病や急性の病気には、薬が必要な時もあるでしょう。大きなケガや病気をしたら、手術のお世話になることもあると思います。
そのような時に分子栄養学ができることは、常日頃から
・細胞レベルで免疫に十分働いてもらえるような生体内の最適な環境を用意しておくこと
・エネルギー代謝経路に関わる栄養素を十分に補充すること
・エネルギー代謝やストレスで産生される活性酸素などに抗酸化栄養素などで対抗すること
などによる身体づくりです。分子栄養学では個々の栄養素の働きを生かし、健康を十分に維持増進できるオプティマムヘルス(最適な健康)、身体づくりを目指します。
※1 参考文献:清野宏.臨床粘膜免疫学.株式会社シナジー, 2010,p.317-330.